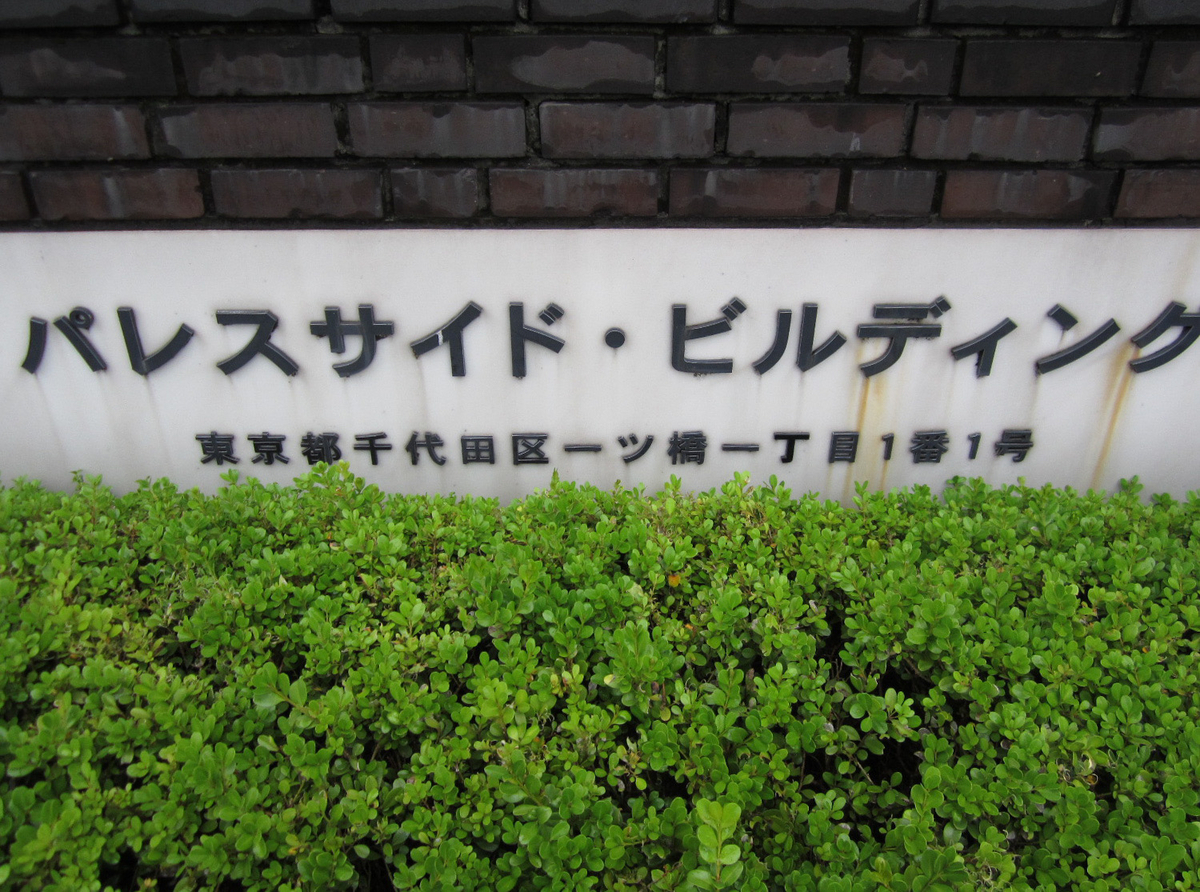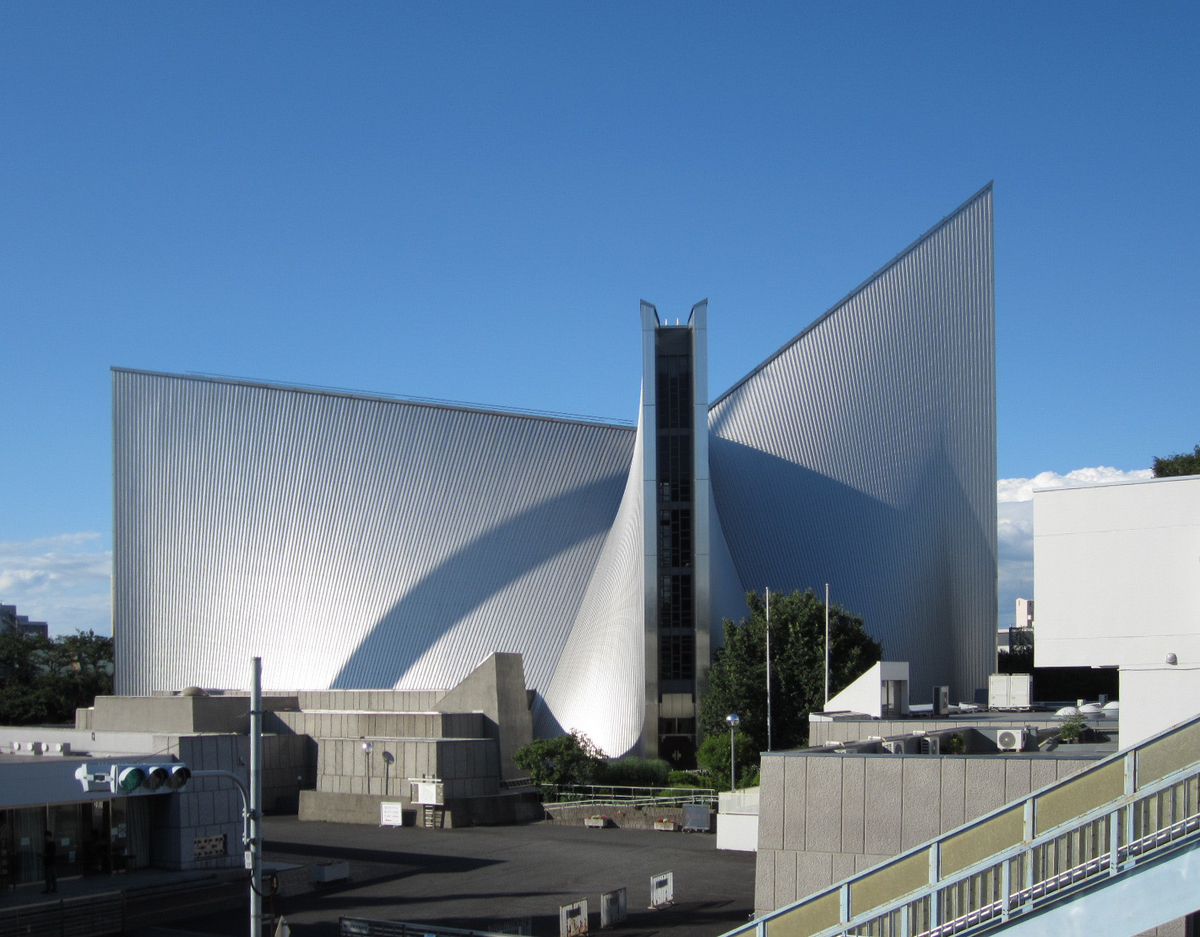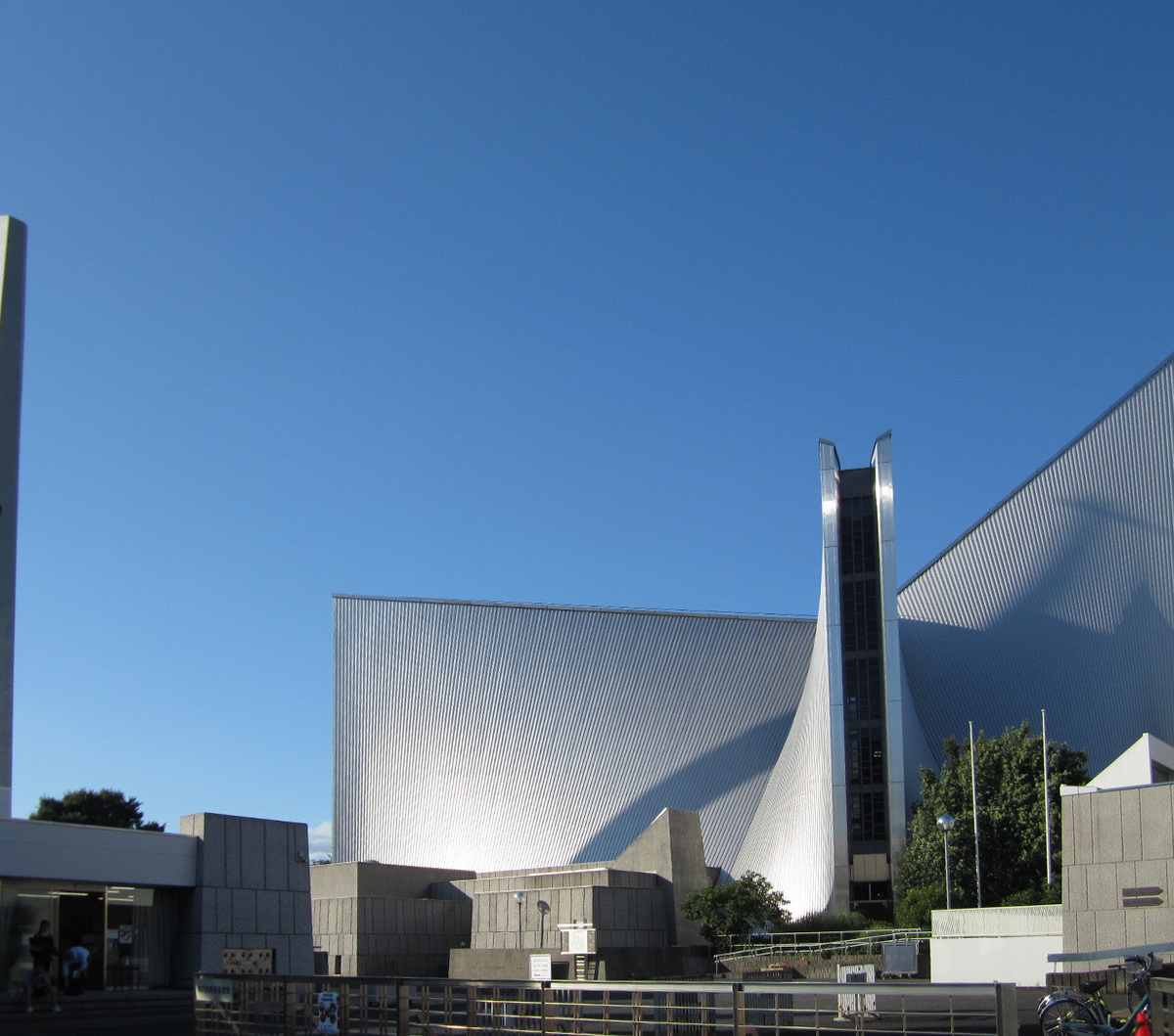不動産業界のデジタル化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が着々と進んでいる。業務を効率化し、それによって新たに生み出された時間で顧客とのコミュニケ―ションを深めたり、蓄積されたデータを活用してビジネスモデルの変革を行っていくことが不動産業界の進化につながっていく。
電子契約の普及・拡大も確実視されている。なにしろ生まれたときからIT(情報技術)やスマホに慣れ親しんできている世代がこれからの顧客となってくる。今はまだ対面や紙を使った契約を希望する人の割合が多いようだが、いずれは逆転していくことになる。膨大な情報にどこからでもアクセスでき、瞬時に処理・活用できるICT(情報通信技術)によるタイムパフォーマンンス効果を身に着けた世代がなんにつけ、その利便性を手離すことはあり得ないからだ。
ICTが苦手と言われる中小不動産業者も心配するに及ばない。従業員の世代交代が進めば自然に解消していく問題だからである。本当の問題はその先にある。事業者と顧客との通信がすべてデジタル化され、そこにAIによるチャット能力が加われば、〝人間力〟の出番がなくなっていく。「人にしかできないことは必ずある」と簡単に片づけてはいけない。
携帯電話やメールの普及で古い世代は人間関係の機微を忘れ、若い世代はそもそもそうしたものの存在を知らないように思う。「AI効果」という言葉がある。AIが進化するにつれ、昔の簡単なAIをAIとは思わなくなることを言う。例えば昔はカシオの計算器に驚いたものだが、今はお掃除ロボットにさえ驚かない。
つまり、人間は機械文明が発達するにつれ、その感性も凡庸化していく生き物なのだ。「人にしかできないこと」は何かという議論で、住宅購入を検討し迷っている顧客を最後に決断させるのは担当者の人間力だという言い方がある。しかし、その人間力の劣化に担当者自身も顧客のほうも気付かない時代がすでに始まっているとしたらどうなるのか。
どんなにAIが進化しても、人にしかできないことは必ずあるというならば、人の脳と、人がつくる人工知能(AI)とはどう違うのかを明確に説明する必要がある。しばしばAIに心はないというが、心とはなにか。簡単にいえば「感情」だが、人間が感情を抱くのはその時々の目的を果たすためだという〝目的論〟を唱える心理学者もいる。ならば、AIにある目的を果たすためには、こういう感情(怒り、悲しみ、喜び、称賛など)を表現すればよいと学習させれば、AIが心を持ったことにならないか。
デジタル化の進展が人間からリアリティ(たとえば人間関係の機微に気付くことなど)を奪い、タイムパフォーマンス意識が現代人の行動を形骸化していないかという懸念を抱き続けることが、人にできる唯一のことと言えば言い過ぎだろうか。
執筆者
 本多信博氏 住宅新報 顧問
本多信博氏 住宅新報 顧問
1949年生まれ。長崎県平戸市出身。早稲田大学商学部卒業。住宅新報編集長、同編集主幹を経て2008年より論説主幹。 2014年より特別編集委員、2018年より顧問。
著書:『大変革・不動産業』(住宅新報社・共著)、『一途に生きる!』(住宅新報社)、『百歳住宅』(プラチナ出版)、『住まい悠久』(同)、『たかが住まい されど、住まい』(同)、『住文化創造』(同)など
現在、住宅新報に連載コラム「彼方の空」を執筆中。